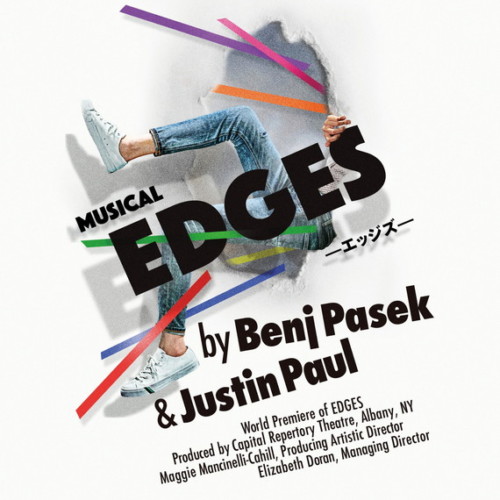柿澤勇人インタビュー 『ハルシオン・デイズ2020』 「見終わった頃には「生きなきゃ」ってポジティブな気持ちが湧き上がる」

――柿澤さんは、舞台だけでなく映画やドラマでも活躍されています。改めて、舞台の魅力はどんなところにあると感じますか?
やっぱり、“生もの”でスタートしたら台本の終わりまで続けなきゃいけないところじゃないですか。本番中にカットなんてできないわけだし、その日に生まれるもの、感じるものって公演ごとに違ったりもする。当然でしょうけど、初日と千秋楽ではぜんぜん違うし。
それと観客の空気感って映像では味わえないですよね。「観てる人がどう感じてるんだろう?」って、若干こちら側にも伝わってくるんですよ。「あ、オレ今スベッた」とか「今オレ、すっげー見られてる!」とか(笑)、日によってぜんぜん違うんですけど。そういう感覚を楽しめるのも舞台ならではだなと思いますね。

――本番中もすごく冷静なんですね。演じながらも全体を見渡しているというか。
僕はすっごい冷静です。ただ、人によってそれぞれですね。「憑依しちゃってなにも覚えてない」って言う人もいるんですけど、僕はそこまでいかない。たとえ激しいシーンで錯乱状態の芝居をするとしても、「今自分は舞台上のどこにいて、どういう姿勢でいる」みたいなことを常に俯瞰して見てるタイプですね。

――「ミュージカル」と「ストレートプレイ」とで、意識の違いはありますか?
「ミュージカルだからこうだ」「ストレートプレイだからこうしなきゃ」と意識して変えてることはないですね。どっちも作品のメッセージを伝えることが本望であり到達点。大きなところでの違いはないと思います。
ただ、どうしてもミュージカルって歌があるので、難しい曲があったらそこに稽古の時間を割かれちゃうんですよ。そのことで、歌の間の芝居がおろそかになったり、歌のことで精一杯になってほかの部分が歯抜けになっちゃったりすることもあって。その点だけで言うと、ストレートプレイは芝居の稽古だけに集中できるっていうよさがありますね。
もちろんミュージカルも、ちゃんと準備して見せられること、面白いキャストや演出家と出会えた時の喜びはなにものにも代えがたいものがあります。そんな作品があればぜひ出たいですね。
完璧なものなんて絶対ない、でも完璧なものを求めなきゃいけない
――柿澤さんが舞台に立っていて幸せを感じるのはどんな瞬間ですか?
カーテンコールで、やっと観客一人ひとりの顔がはっきり見えた時に「喜んでくれてるんだろうな」って感じる瞬間はもちろん幸せです。ミュージカルで格好いい曲とか大曲を歌った後に歓声をもらうのって役者としてはすごく嬉しくて。それでテンションが上がっていって、すごくいい作品になる時があると思うんです。
ただ、今はマスクが必須で、スタンディングオベーションもできなければ大きな声も出せない。ここ1~2年はそれが続くでしょうから寂しいなと思いますね。
それから、これは映像もそうですけど、役者って虚構を演じるわけですよね。自分じゃない役の言葉をしゃべる。でも、10回に1回くらいなにも考えてなくてもポロッとセリフが出る瞬間があるんですよ。
「あ、この感覚でぜんぶできたらいい役者になるんだろうな」と思うんですけど、そんなことは本当に稀で(笑)。「あ、言えた」って気づいた時に幸せを感じますね。どうしてもキャリアを重ねていくと、いろいろ考えて技術的に「こうしたほうがおいしい」とかって部分が出てきちゃうので。
そういう意味では、今回共演する須藤くんのように“狙ってない芝居”を観るとすごく新鮮ですね。ぜんぜん経験値がない人の芝居のほうが、もしかしたらピュアなのかもしれない。まぁこれって役者の方なら、たぶん誰もが感じているところだと思うんですけど。完璧なものなんて絶対ない、でも完璧なものを求めなきゃいけないっていう。果てしない難題ですよね。

――お芝居の世界は奥深いですね。そんな柿澤さんが刺激を受けている役者さんはいらっしゃいますか?
いろんな人に刺激を受けてます。あこがれというか、永遠のアイドルみたいな人はジェームズ・ディーン。今生きてる方だと、エドワード・ノートンとライアン・ゴズリング。二人が出ている作品はぜんぶ観てます。 身近なところで言うと、今度二人芝居で共演する吉田鋼太郎さん。刺激になるし、ずっと背中を追い続けていくんだろうなって存在ではありますね。ちなみに「鋼太郎さんみたいになりたい」とは思わないです。結婚するなら1回でいいと思うので(笑)。