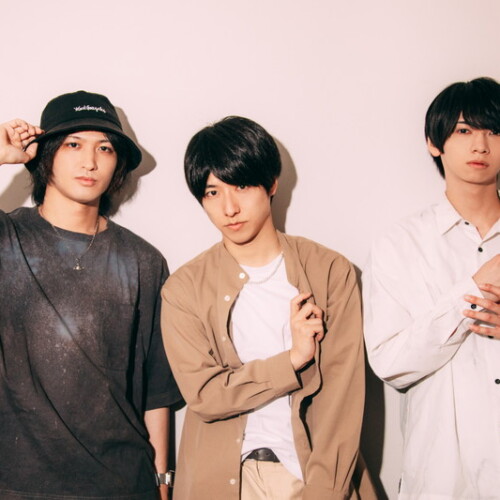演出家・荻田浩一×元吉庸泰対談インタビュー ミュージカル『EDGES ―エッジズ―』 個性の異なる2チームそれぞれの魅力とは(前編)
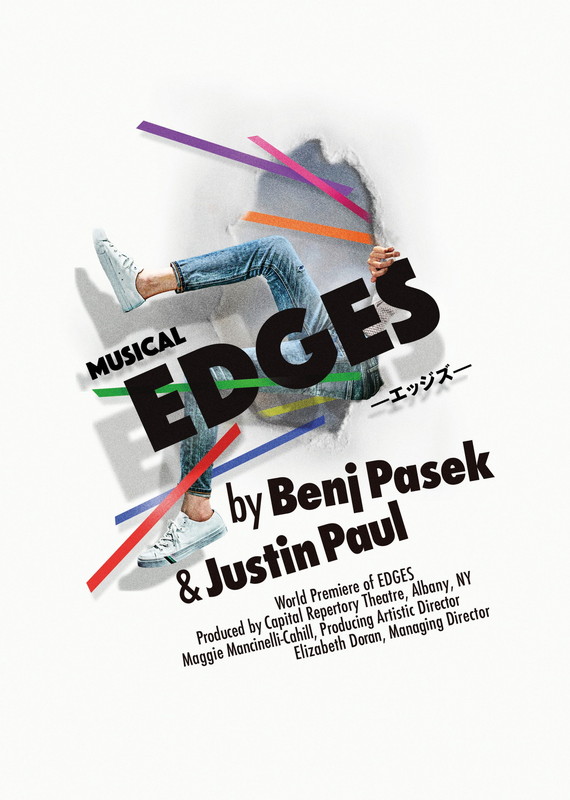
――本作は、映画「ラ・ラ・ランド」の歌詞、「グレイテスト・ショーマン」の楽曲を手掛けた作詞・作曲家デュオ、ベンジ・パセック&ジャスティン・ポールが学生時代に書いたデビュー作で、日本初演となる作品です。作品自体には、どんなところに魅力を感じましたか?
元吉:“ソングサイクル”形式のミュージカルなので、基本的に一曲一話で完結していくというのが前提にあります。最初に聴いた印象は、「お話を聞いてよ」と言ってくる感じが強かったというか。二人がこの曲を作ったときに、「自分たちが何者なのかはわからないけど、そんなことどうでもいいよね」みたいな。
ちょっとシニカルさも入れつつ、ちゃんと理想に手を伸ばすといった感じで。 ものすごく若々しさを感じたんですよね。「わざと剛速球を投げてみるけど、キャッチもしなくていいし、打ち返しもしなくていい、ただ、僕らは球を投げるよ」みたいな。そういうちょっと挑戦的なイメージを全曲に感じました。
僕らがやっているのは2007年に上演された再演の曲です。2005年の初演のときは全体的に曲のバランスがキャッチーだったんですよね。ただ、2007年の再演のときは、キャッチーさというよりは、「僕ら、世の中をナメてます」みたいな印象で(笑)。それをどういう風に歌い繋いで遊んでいくかっていうのを問われるのは、従来のミュージカルには全くないものですし、面白さを感じました。
ソングサイクル形式のミュージカルって、なにか一つのテーマがもう少し色濃く出てるものなんですけど、今回はそのテーマも、「そこに味付けをするのはお前たちじゃない?」みたいな、ものすごく薄味な印象で。でもそれも、彼らからのメッセージなのかなと感じたので、演出するからにはちょっと塩コショウをふって頑張ろうかなと思います。
荻田:やっぱり楽曲の良さですかね。“ソングサイクル”というスタイルで、一曲一曲、オムニバスになる訳ですけど。楽曲で語られていることってわりと他愛のないことが多くて。そういう意味では日常生活であり、深刻な物語ではないんですよ。だから、肩に力が入らず、わりとするっと聴けちゃう印象でした。でも、聴いてるうちにちょっとやみつきになるフレーズや、ついつい口ずさんじゃう感じもあったり。
あとは、元吉さんがおっしゃっていたように、作詞作曲を手掛けた彼らが、若いときに作ったので、ほかのミュージカルの著作権には引っかからない程度に、何小節かだけ「ちょっとこれをまぶしてみよう」みたいな遊び心もあるし。きっと彼らなりの自由な遊び心で作った作品なのかなと思います。
だから僕らも自由に遊ばなければ、きっとこの作品の魅力が出せないと思うんです。なので、もちろん真面目に稽古はするんですけど、めったにミュージカルの現場では言わないような、「好きに歌って」とか「どんどん崩して」みたいなことを歌稽古で指示していたりします(笑)。むしろ、歌い手がシンガーソングライターのように、彼らが思うことを歌っているように聴こえないとだめだし。とくにソロだと長いので、より、キャラクターを個々の中で明確にする必要があると思うんです。
先ほどもお話ししましたけど、僕のチームはコンサートっぽい感じなので、演出家としては、一つのドラマを歌い手さんの中に作っていただいて、聴かせるというか。一人の漫談というか、スタンダップコメディにも通ずるものがあるかもしれません。綾小路きみまろさんのようにならないとだめだって、僕はよく言ってるんですけど。歌い手が遊んでくれて、お客様も心の中で遊んでいただけたらいいなと思いますね。